「UNIX」と「Linux」って授業でよく聞くけど、正直どう違うの?そんな疑問を持つ初心者のために、高校生でもわかるレベルでやさしく解説します。
専門用語はなるべく使わず、例え話も交えながら、UNIXとLinuxの基本からその関係性までスッキリ整理してお伝えします!
UNIXとLinux、違いの背景とは?
「UNIXとLinuxって、どっちもOSらしいけど何が違うの?」そんな疑問を持つ初心者の方は多いと思います。
実は、2つの違いを理解するには、まず「OSとは何か?」をざっくり知っておくとスムーズです。
OS(オペレーティングシステム)とは、パソコンやスマホを動かすための“基本のソフトウェア”のこと。
つまり、私たちがアプリを使ったり、ファイルを保存したりできるのは、このOSが裏で働いてくれているからなんです。
さて、UNIX(ユニックス)はそのOSの中でも、歴史がとても長いものです。
1970年代にアメリカのAT&Tベル研究所で開発され、大学や企業の研究機関で広く使われるようになりました。
とくに学術系で人気があり、多くの派生バージョン(「◯◯ UNIX」など)が誕生していきました。
UNIXは「安定していて信頼できるOS」として評価され、大型サーバーやシステム開発の現場で活躍してきました。
一方、Linux(リナックス)は1991年、フィンランドの大学生だったリーナス・トーバルズという人物が、自学のためにUNIXの仕組みをまねて作り始めたOSです。
驚くべきことに、このLinuxは無料で誰でも使えることを大きな特徴としています。
オープンソースと呼ばれるこの仕組みのおかげで、世界中のエンジニアがLinuxの改善に貢献できるようになり、瞬く間に広まりました。
つまり、UNIXとLinuxの違いの背景には、「誰が作ったか」「いつ作られたか」「どのように広まったか」といった歴史的なポイントがあります。
UNIXは企業や大学の研究者によって設計された商用ベースのOS。
一方でLinuxは、学生が個人の興味から生み出した自由で開かれたOS。
そこに大きな違いがあるのです。
また、UNIXは基本的に有償で、使うにはライセンス契約が必要なのに対し、Linuxは無償で利用可能。
ここもUNIXとLinuxの違いとしてよく話題にされるポイントです。
ちなみに、macOSはUNIX系の流れをくむOSであり、AndroidはLinuxベースのOSなんですよ。
まとめると、UNIXとLinuxは見た目が似ていたり、コマンド操作が共通していたりするため混乱しがちですが、成り立ちや考え方にはしっかり違いがあります。
この違いの背景を知ることで、今後それぞれのOSに触れるときの理解が深まりますよ。
UNIXとLinuxの違いを具体例で解説
前のセクションでは、UNIXとLinuxの背景についてお話しました。
では実際に、どんなところでUNIXとLinuxの違いが現れるのでしょうか?
ここでは、具体的な例を使って「unixとlinuxの違い」をわかりやすく解説していきます。
まず、使われている場所の違いから見てみましょう。
UNIXは、主に大企業の基幹システムや銀行、官公庁などの安定性が最優先される分野で使われています。
たとえば、銀行の取引システムや航空券の予約システムなどで「絶対に止まってはいけない」場面で活躍しています。
こういった現場では、信頼性の高いUNIXベースのOS(たとえばAIXやHP-UXなど)が採用されていることが多いです。
一方で、Linuxはより身近なところで使われています。
たとえば、Androidスマホの内部にもLinuxが使われていたり、Webサイトを動かすサーバーとしてもLinuxは大活躍しています。
たとえば、YouTubeやAmazonなどの巨大サイトの多くはLinuxで動いていますし、自宅で使う「ラズベリーパイ(Raspberry Pi)」という小型コンピュータにもLinuxがよく使われています。
もうひとつの具体的な違いは「導入のしやすさ」です。
UNIXは基本的に商用で、使うにはお金がかかったり、企業向けのライセンスが必要になります。
個人が気軽に試すにはハードルが高めです。
それに対して、Linuxはインターネットから誰でも無料でダウンロードして使えるので、大学の授業や独学でも手軽に試せます。
UbuntuやFedora、Debianなど、初心者向けのLinuxディストリビューションも多数あり、学習しやすいのも特徴です。
コマンド操作についても触れておきましょう。
UNIXとLinuxは、使われるコマンドがかなり似ています。
たとえば「ls」や「cd」、「mkdir」などの基本的な操作は共通しています。
しかし、ディストリビューションやシステム構成によっては微妙な違いが出ることもあります。
とはいえ、初心者の段階では「基本は同じ」と覚えておけば問題ありません。
このように、UNIXとLinuxの違いは「どこで使われているか」「誰が使うか」「どんな目的か」という具体的な場面によって分かりやすく見えてきます。
簡単にまとめると、
- UNIX:企業向け・安定性重視・有償
- Linux:個人でも使いやすい・自由にカスタマイズ可能・無償
このように、実際の用途や特徴を比べると、UNIXとLinuxの違いがぐっと理解しやすくなりますね。
UNIXとLinuxの違いを初心者が説明するなら
もし友達に「UNIXとLinuxの違いって何?」と聞かれたら、どう答えればいいでしょう?
自分がちゃんと理解していないと、うまく説明できないし、自信もなくなってしまいますよね。
でも大丈夫。
ここで基本のポイントを押さえれば、自然と言葉にできるようになります!
まずはこう言ってみましょう。
「UNIXは昔からある高性能なOSで、Linuxはその流れをくんだ無料のバージョンみたいなものだよ。」
これだけで「お、わかってるじゃん!」と思ってもらえる可能性大です。
もう少し説明すると、「UNIXは1970年代に作られて、企業や研究所でよく使われてきた有料で安定したOS」。
「Linuxは1991年に大学生が作り始めた無料で誰でも使えるUNIX風のOS」という感じです。
たとえば、こんなふうに説明してもOKです。
「UNIXはしっかりしたスーツを着たビジネスマン、Linuxは自由な服装で仕事するフリーランス、みたいなイメージ!」
つまり、目的は似てるけど、使う人やルールが違うってことですね。
また、こう言うとイメージしやすいです。
「UNIXは銀行とか病院のシステムで使われてて、LinuxはスマホとかWebサーバーとか、自分たちが触れる場所にもけっこう使われてるんだよ。」
このように、どこで使われているかの具体例を交えると、聞いてる人も「へぇ〜」となりやすいです。
そして最後に、こんなまとめ方をすれば完璧。
「要するに、UNIXはプロ向けで有料、Linuxは自由でオープン。中身は似てるけど、使い方や広がり方がぜんぜん違うってことだね。」
このように、自分の言葉で説明できるようになれば、UNIXとLinuxの違いをちゃんと理解できた証拠です。
初めは難しく感じるかもしれませんが、少しずつ言葉にしていくことで、知識はどんどん身につきますよ!
UNIXとLinuxの違いの知識を活かそう
UNIXとLinuxの違いを理解できたら、それはIT学習の大きな一歩です。
ここで得た知識は、単なる豆知識ではなく、これから学んでいくプログラミングやサーバー、ネットワークの分野でもしっかり役に立ちます。
たとえば、Linuxは大学の授業や演習環境でもよく使われていますし、自分のパソコンにLinuxをインストールして遊んでみるのも良い経験になります。
Ubuntuなど初心者向けのディストリビューションを使えば、簡単に触ることができますよ。
また、UNIXやLinuxに関する基本コマンドを少しずつ覚えていくことで、プログラミングやシステム操作の理解も深まります。
ターミナル操作が苦手なうちは、実際に打ちながら覚えるのが一番です。
「UNIXとLinuxって、何が違うの?」と誰かに聞かれたとき、今日の自分なら少し自信を持って答えられるはず。
知識を「覚える」だけでなく、「使ってみる」ことこそが、次の成長につながります。

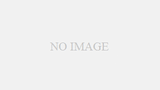
コメント